捨てる決断が会社を救う – 実行支援型コンサルが見た不採算部門との向き合い方
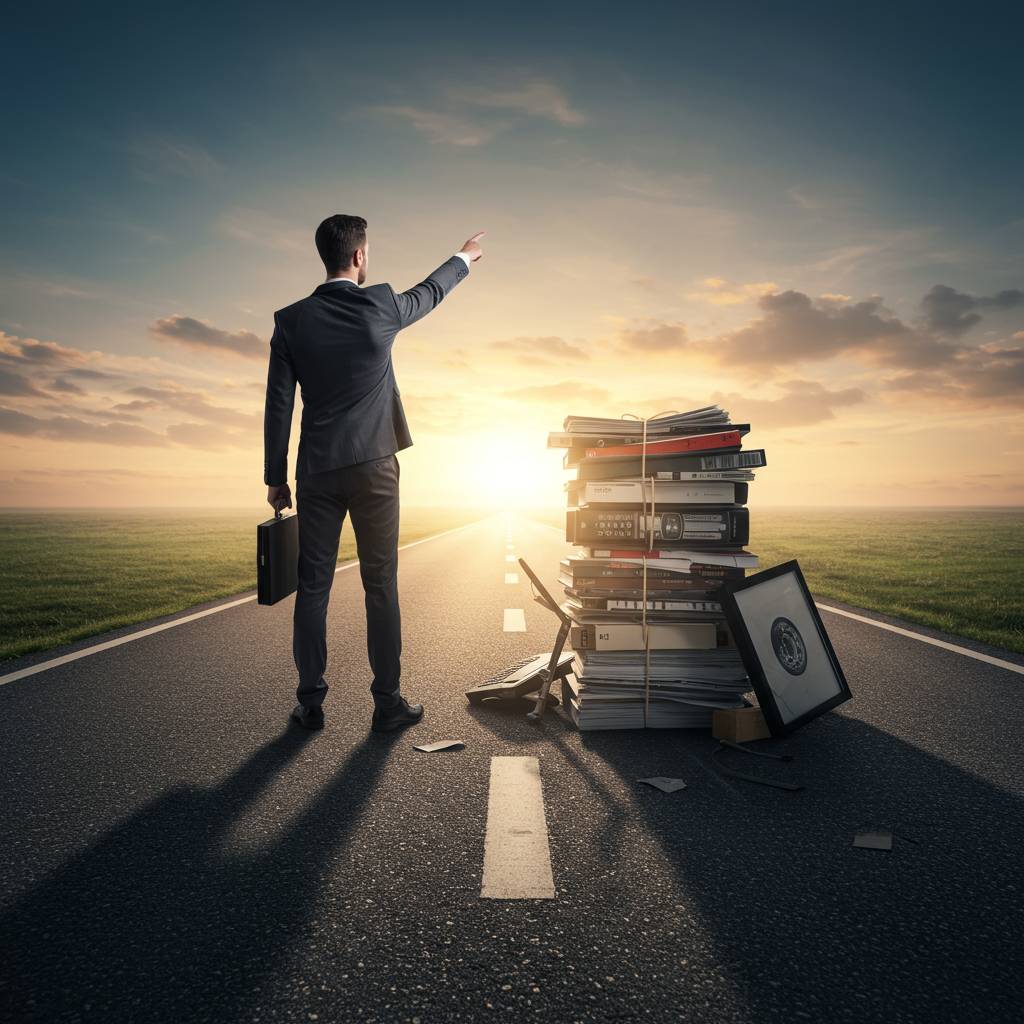
こんにちは。経営改革の現場で多くの企業と向き合ってきた経験から、今日は「捨てる決断」についてお話しします。
「この事業は先代から続いているから」「社員の雇用を守るため」「いつか黒字になるはず」—そんな思いで不採算部門を抱え続けていませんか?
実は、日本企業の多くが直面するこの課題に、明確な答えを持てずにいます。経済産業省の調査によれば、中小企業の約40%が不採算事業を抱えたまま経営を続けており、それが全体の収益性を圧迫している実態があります。
私がコンサルタントとして関わった製造業A社は、思い切って売上の15%を占める赤字部門を整理した結果、翌年には利益率が2倍に向上。B社は不採算事業からの撤退により、本業への投資資金を確保し、3年で売上30%増を達成しました。
しかし、この「捨てる決断」は決して簡単ではありません。社内の反発、顧客への影響、社会的評価など、乗り越えるべき壁は高いものです。
この記事では、実際の成功事例と失敗事例から学ぶ、不採算部門との向き合い方と、その先にある企業成長の可能性についてお伝えします。経営者だけでなく、事業部責任者や将来の経営幹部を目指す方にも、ぜひ参考にしていただきたい内容です。
1. 「赤字部門を手放す勇気 – トップ企業が実践する経営改革の秘訣とは」
企業経営において、赤字部門の存続問題は永遠のジレンマです。「何年も赤字だが、将来性があるから」「主力事業とのシナジーがあるから」という理由で不採算部門を抱え続ける企業は少なくありません。しかし、真に会社を成長させるためには「捨てる決断」が時に不可欠です。
日本を代表する企業、ソニーグループは2014年にVAIO事業を売却し、テレビ事業を分社化するという大胆な決断を下しました。当時は批判の声も多かったものの、この決断が後の収益構造改革の礎となり、現在の業績回復につながっています。同様に、コニカミノルタがカメラ事業から撤退し、ビジネスソリューションへと舵を切ったことも、「捨てる経営」の好例です。
不採算部門を抱え続ける最大の問題は、限られた経営資源の分散にあります。人材、資金、時間という有限のリソースが赤字部門に吸収され、成長の見込める事業への投資機会を失っているケースが多々あります。ある中堅製造業では、売上の5%に満たない不採算事業に経営陣の30%以上の時間が割かれていたという衝撃的なデータもあります。
「捨てる」という選択肢には様々な形があります。完全撤退だけでなく、事業売却、分社化、合弁会社設立など、状況に応じた最適解を見つけることが重要です。富士フイルムホールディングスは写真フィルム事業の縮小を決断する一方で、培った技術を医療や化粧品分野へと展開し、見事な事業転換を成し遂げました。
経営者が「捨てる決断」を躊躇する背景には、しばしば感情的な要因があります。創業者が立ち上げた事業、自身が携わってきた部門への愛着、従業員の雇用への配慮など、合理的判断を鈍らせる要素は多岐にわたります。しかし、リーダーとしての責任は、会社全体の存続と発展にあることを忘れてはなりません。
トップ企業の経営改革に共通するのは、客観的なデータに基づく冷静な意思決定プロセスです。過去の実績や感情ではなく、将来性と全社的な資源配分の観点から各事業を評価する習慣が根付いています。GEが導入した「No.1かNo.2になれない事業からは撤退する」という明確な基準設定も、参考になる手法です。
不採算部門との決別は痛みを伴いますが、それを乗り越えた企業の多くが、より強靭な収益構造と明確な事業戦略を手に入れています。真の経営力とは、何を始めるかだけでなく、何を終わらせるかを決断できる力なのかもしれません。
2. 「不採算事業からの撤退で売上30%増 – 成功企業に学ぶ”捨てる決断”の具体的手法」
「収益性の低い事業を手放すことで、会社全体が息を吹き返した」。これは大手電機メーカーの子会社であるA社の経営者が語った言葉です。A社は長年赤字を垂れ流していた海外向け家電部門から撤退し、代わりに国内のBtoB事業に経営資源を集中投下。その結果、撤退から1年後には売上高が30%増加し、営業利益率も2%から8%へと飛躍的に向上しました。
不採算事業からの撤退は「敗北」ではなく「戦略的な選択」です。日本企業の多くが「捨てる決断」を先送りにする傾向にありますが、実際には事業を適切に整理することで成長が加速するケースが数多く存在します。
成功企業が実践する「捨てる決断」の具体的手法は以下の通りです。
1. 数値による冷静な判断基準の設定
成功企業は感情論ではなく、明確な基準で判断します。例えば、カルビーは「ROA15%未満の事業は再構築対象」という明確な基準を設け、低収益事業からの撤退を実現しました。自社に合った「捨てる基準」を設定することが第一歩です。
2. 段階的な撤退プロセスの設計
一気に撤退するのではなく、段階的なプロセスを踏むことで混乱を最小化します。ソニーはPC事業「VAIO」からの撤退時、合弁会社設立による段階的な事業移管を行い、顧客サポートや従業員処遇に配慮しました。
3. リソースの再配分計画の策定
撤退で浮いたリソースの再配分先を事前に明確化します。パナソニックは不採算だったプラズマディスプレイ事業から撤退し、自動車関連や住宅設備事業へと経営資源をシフト。この明確な再配分戦略が新たな成長エンジンを生み出しました。
4. 社内コミュニケーションの徹底
「なぜ捨てるのか」を社内に丁寧に説明することで、士気低下を防ぎます。ヤマハ発動機は採算の取れなくなった一部の楽器事業からの撤退時、全社員に対して「モーターサイクル事業への集中が会社の未来を支える」と明確なビジョンを示しました。
5. 撤退後の検証プロセスの確立
撤退後の効果測定を行い、次の判断に活かします。花王は定期的な事業ポートフォリオ検証会議を設け、撤退判断の妥当性を振り返る文化を構築しています。
実際、経営コンサルティング大手のマッキンゼーの調査によれば、戦略的に事業撤退を行った企業の約60%が、その後3年以内に全社の収益性が向上したというデータがあります。
重要なのは「捨てる」という行為自体ではなく、限られた経営資源を最も成長可能性の高い分野に再配分することです。不採算事業に固執せず、適切なタイミングで「捨てる決断」ができる企業こそが、激変する市場環境の中で持続的な成長を実現できるのです。
3. 「社員の反発を乗り越えて黒字化 – コンサルタントが明かす不採算部門整理の現場」
不採算部門の整理は避けて通れない経営判断ですが、最も困難なのは社内の反発への対応です。ある製造業では、30年続いた主力製品の生産ラインを閉鎖する決断に直面しました。この部門には20名のベテラン社員が所属し、「自分たちの居場所がなくなる」という不安から強い抵抗がありました。
まず着手したのは「数字による現状の可視化」です。部門別採算を徹底的に分析し、この部門が年間8,000万円の赤字を生み出し、他部門の利益を圧迫している事実を全社員に共有しました。次に「代替案の提示」として、対象社員の70%を成長部門へ異動させる計画を立案。残りの社員には早期退職プログラムを用意し、再就職支援も含めた手厚いケアを約束しました。
最も効果的だったのは「将来ビジョンの共有」です。不採算部門の整理によって生まれる資金を、IoT技術を活用した新製品開発に投資する具体的な成長戦略を示しました。これにより「会社全体が生き残るために必要な決断」という認識が社内に広がりました。
実行段階では抵抗も予想されましたが、経営陣が現場に足を運び、一人ひとりと対話を重ねることで信頼関係を構築。結果的に予定より1ヶ月早く部門整理が完了し、翌期から3,000万円の黒字転換に成功しました。さらに2年後には新製品が売上の15%を占めるまでに成長しています。
ポイントは「データによる説得」「影響を受ける社員への真摯な対応」「会社の未来像の共有」の3つです。不採算部門の整理は単なるコスト削減ではなく、企業の持続的成長のための積極的な投資判断であることを全社で共有できれば、社員の反発を最小限に抑えながら企業変革を実現できるのです。
【監修者】ブルーリーフパートナーズ
代表取締役 小泉 誉幸
公認会計士試験合格後、新卒で株式会社シグマクシスに入社し、売上高数千億の大手企業に対し業務改善、要件定義や構想策定を中心としシステム導入によるコンサルティングを実施。その後、中堅中小企業の事業再生を主業務としているロングブラックパートナーズ株式会社にて財務DD、事業DD、再生計画の立案、損益改善施策検討に従事。ブルーリーフパートナーズ株式会社設立後は加え税理士法人含む全社の事業推進を実施。
・慶應義塾大学大学院商学研究科修了
