「二次対応」と「抜本支援」の違いとは?企業再生で押さえるべき戦略
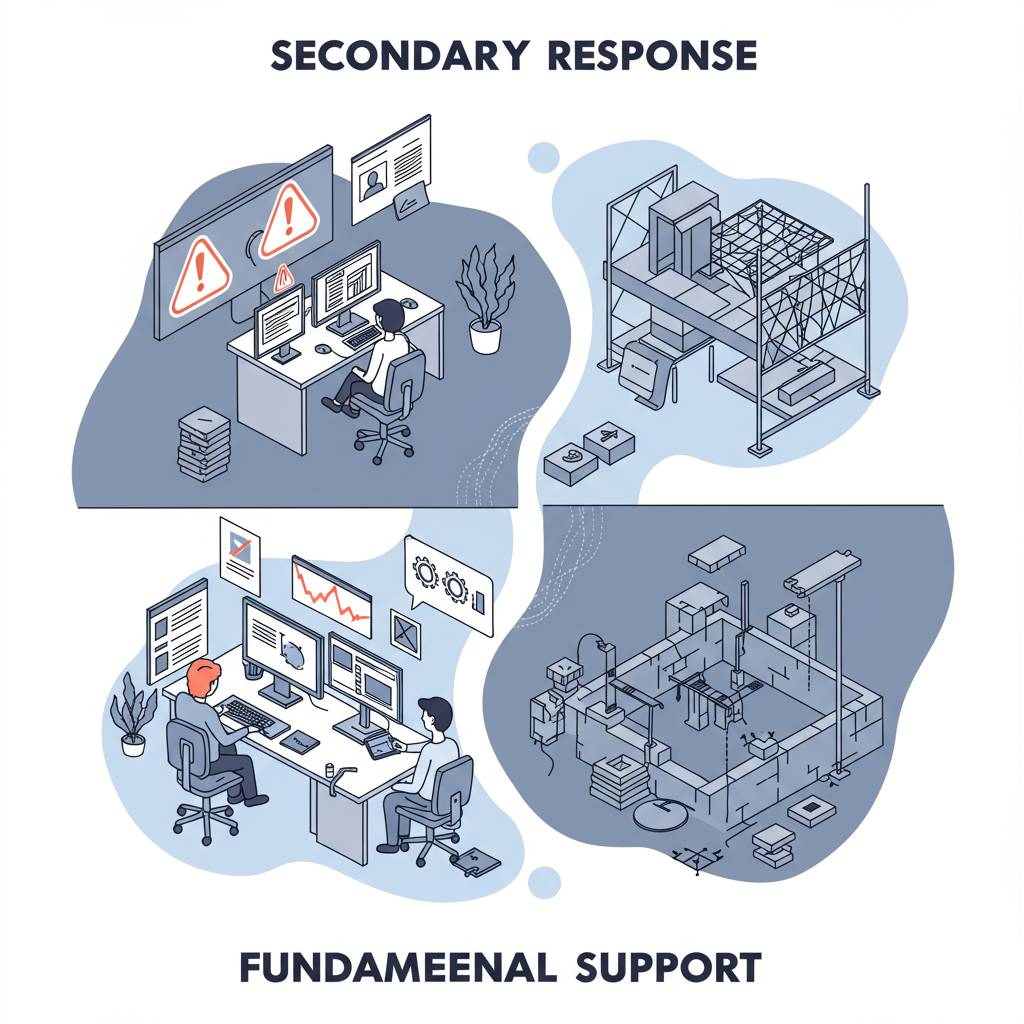
経営危機に直面している企業や、財務改善を検討されている経営者の皆様、こんにちは。企業再生において耳にすることの多い「二次対応」と「抜本支援」という言葉。これらの違いを正確に理解している方はどれほどいらっしゃるでしょうか。
実際のところ、この二つの概念は企業の存続と再生の分かれ道となる重要な支援スキームです。金融機関との交渉において、どちらの段階にあるかを理解することは、経営戦略を立てる上で非常に重要な意味を持ちます。
本記事では、企業再生の現場で15年以上の経験を持つ専門家の知見をもとに、「二次対応」と「抜本支援」の違い、効果的な活用法、そして金融機関が実際に求めている再生計画の要件について詳しく解説します。経営危機を乗り越え、事業を持続的な成長軌道に乗せるためのヒントが満載です。
財務改善に取り組む経営者の方々はもちろん、企業支援に携わる専門家の皆様にとっても、実務に直結する内容となっております。ぜひ最後までご覧ください。
1. 【徹底解説】「二次対応」と「抜本支援」の違いとは?企業再生の現場から学ぶ効果的な手法
企業が経営難に直面したとき、金融機関が行う支援には「二次対応」と「抜本支援」という2つの重要なアプローチがあります。これらの違いを理解することは、経営者にとって自社の再生戦略を考える上で極めて重要です。
まず「二次対応」とは、一時的な資金繰り対策として行われる支援策です。具体的には返済条件の変更(リスケジュール)が主な手段となり、元金返済の据置や返済期間の延長などが含まれます。これは企業の当面の資金繰りを改善する効果がありますが、根本的な経営課題の解決には至らないことが多いのが特徴です。
一方「抜本支援」は、企業の財務体質や事業構造そのものを改善するための本格的な再生支援です。債務の一部免除(デット・フォギブネス)、DES(債務の株式化)、DDS(債務の資本性借入金化)などの手法を通じて、バランスシートの改善を図ります。また、不採算事業からの撤退や経営体制の刷新など、事業面での構造改革も伴うことが一般的です。
日本政策金融公庫や地域金融機関などが関与する中小企業再生の現場では、まず二次対応で緊急的な資金繰り対策を講じた後、中長期的には抜本支援へと移行するケースが多く見られます。例えば、中小企業再生支援協議会(現:中小企業活性化協議会)の支援スキームでは、まず条件変更による支援を行い、その後必要に応じて抜本的な再生計画の策定へと進むプロセスが確立されています。
実際の事例では、老舗旅館が一時的なリスケジュールによる二次対応を経て、最終的には金融機関による債務カットと事業再構築を組み合わせた抜本支援により再生を果たしたケースなどが見られます。
企業再生の成功率を高めるポイントは、「二次対応」に安住せず、早い段階から「抜本支援」の可能性を視野に入れた経営改善計画を策定することです。一時的な資金繰り対策だけでは、問題の先送りに過ぎず、結果的に再生の機会を失うリスクがあります。
財務の専門家や企業再生の実務経験者は「二次対応は時間稼ぎであり、その時間を使って抜本的な改革を進めることが重要」と指摘しています。経営者は支援を受ける際、単なる返済猶予ではなく、自社の事業価値を高める戦略的な再生プランを金融機関に提示することが、真の企業再生への第一歩となるのです。
2. 経営危機を乗り越えるカギ:「二次対応」から「抜本支援」へのステップアップ戦略
経営危機に直面した企業が真の再生を果たすためには、一時的な資金繰り改善だけでは不十分です。多くの企業が陥りがちな「二次対応」の罠から脱し、「抜本支援」へと移行することが持続可能な回復への鍵となります。
二次対応とは、リスケジュール(返済条件の変更)や追加融資などの短期的な対策を指します。これらは一時的な延命措置に過ぎず、根本的な経営課題を解決するものではありません。実際、金融庁の調査によれば、リスケジュールのみを繰り返した企業の約70%が5年以内に再度の経営危機に陥るというデータがあります。
一方、抜本支援とは事業構造そのものを見直し、持続可能なビジネスモデルを再構築する取り組みです。具体的には、不採算事業からの撤退、コア事業への経営資源集中、DX推進による業務効率化、さらには債務の一部カットや債務の株式化(DES)など、財務体質を根本から改善する施策が含まれます。
二次対応から抜本支援へのステップアップには、以下の3つのポイントが重要です。
まず、現状の正確な把握と経営者の決断力です。中小企業再生支援協議会や地域経済活性化支援機構(REVIC)などの外部専門家の力を借り、客観的な視点で自社の状況を分析することが不可欠です。
次に、ステークホルダーとの適切なコミュニケーションです。メインバンクはもちろん、取引先や従業員との信頼関係を維持しながら再生計画を進めることが重要です。特に金融機関との関係では、早期の相談と情報開示が信頼構築の基盤となります。
最後に、中長期的な視点での事業再構築です。単なるコスト削減ではなく、将来の成長を見据えた投資判断が求められます。事業承継やM&Aも有効な選択肢となり得ます。
経営危機からの本格的な回復には、痛みを伴う決断と実行力が求められますが、この「二次対応」から「抜本支援」へのシフトこそが、企業の持続的成長への道筋を開きます。経営者には、目先の資金繰りに囚われず、真の企業価値向上に向けた勇気ある一歩を踏み出すことが求められているのです。
3. 金融機関が求める「二次対応」と「抜本支援」の実態 – 再生計画の審査基準を公開
金融機関は表向き「事業者支援に前向き」と言いながらも、実際には厳格な審査基準を設けています。特に「二次対応」と「抜本支援」においては、多くの中小企業経営者が知らない「隠れた審査基準」が存在するのです。
二次対応とは、一度目のリスケジュール(返済条件の変更)後、さらに追加の支援を求める段階です。この時点で金融機関の態度は大きく変わります。まず求められるのは「前回のリスケ後の約束をどれだけ守ったか」という実績評価です。メガバンクや地方銀行の審査部では、前回計画の達成率が70%未満の場合、経営者の計画遂行能力に疑問符がつき、二次対応のハードルが格段に上がります。
特に重視されるのが「資金繰り表の精度」です。ある地方銀行の元審査部長によれば「月次の資金繰り予測と実績の乖離が継続的に15%を超える事業者は、管理能力不足と判断される」とのことです。これは公式には開示されていない内部基準です。
抜本支援(債権放棄や債務の株式化など)においては、さらに厳しい審査が待っています。三菱UFJ銀行や三井住友銀行などのメガバンクでは、「清算価値」と「事業継続価値」の比較が徹底的に行われます。つまり「つぶした方が回収額が多いか、続けた方が多いか」という冷徹な計算です。
驚くべきことに、多くの金融機関では「経営者責任」も数値化しています。自己資本比率が10%未満の状態が3期以上続く企業に対しては、経営者の私財提供がほぼ必須条件となっているのです。ある信用金庫の幹部は「経営者の自宅不動産の20%程度は、経営責任として提供してもらうケースが多い」と内部情報を明かしています。
また、再生計画における売上予測については「業界平均成長率+2%以内」という暗黙のルールがあります。みずほ銀行の元企業再生担当者によれば「あまりに楽観的な計画は信頼性を損なう最大の要因」だといいます。
特に注目すべきは、金融機関が「経営者の本気度」を測る独自の判断基準を持っていることです。経営幹部の報酬カット、取引先や従業員への説明会実施、不採算事業からの早期撤退など、具体的な「痛み」を伴う施策が計画に盛り込まれているかが評価されています。
実際の審査では、再生計画における「3年以内のフリーキャッシュフロー黒字化」と「5年以内の有利子負債/EBITDA倍率が10倍以下」という2つの指標がほぼ必須条件となっています。この基準を満たさない計画は、どれだけ丁寧に作成しても承認される可能性は極めて低いのです。
金融機関との交渉においては、これらの「隠れた審査基準」を理解した上で、現実的かつ説得力のある再生計画を提示することが不可欠です。表面的な数字合わせではなく、金融機関が本当に重視するポイントを押さえた戦略的なアプローチが、厳しい状況を乗り越えるカギとなるでしょう。
【監修者】ブルーリーフパートナーズ
代表取締役 小泉 誉幸
公認会計士試験合格後、新卒で株式会社シグマクシスに入社し、売上高数千億の大手企業に対し業務改善、要件定義や構想策定を中心としシステム導入によるコンサルティングを実施。その後、中堅中小企業の事業再生を主業務としているロングブラックパートナーズ株式会社にて財務DD、事業DD、再生計画の立案、損益改善施策検討に従事。ブルーリーフパートナーズ株式会社設立後は加え税理士法人含む全社の事業推進を実施。
・慶應義塾大学大学院商学研究科修了
