事業再生の新常識:ADRを選ぶべき5つの理由
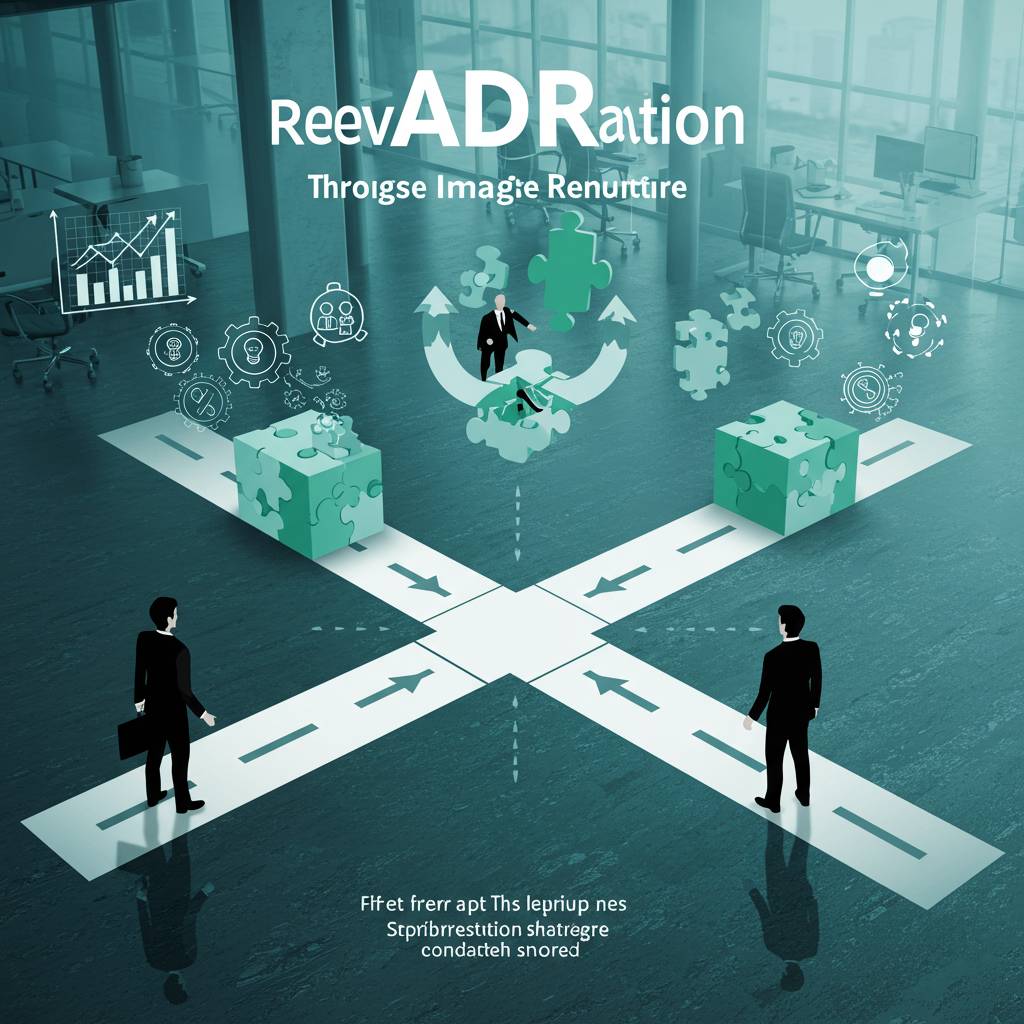
事業再生の新常識:ADRを選ぶべき5つの理由
経営危機に直面した企業が取るべき道は様々ですが、近年注目を集めているのが「事業再生ADR(Alternative Dispute Resolution:裁判外紛争解決手続)」です。従来の法的整理とは異なるアプローチで、多くの企業に新たな選択肢を提供しています。
本記事では、経営再建を目指す企業がADRを選択すべき具体的な理由を5つご紹介します。
1. 企業イメージの保全が可能
法的整理(民事再生・会社更生)と異なり、ADRは裁判所を通さない私的整理の一種です。このため、企業名が官報に掲載されることがなく、「倒産」というレッテルを貼られるリスクが低減されます。
JALの経営再建が記憶に新しいですが、上場企業であっても風評被害によって取引先や顧客が離れていくケースは少なくありません。ADRであれば、日常業務を継続しながら債務整理を進められるため、企業価値の毀損を最小限に抑えられます。
2. 迅速な再生プロセスの実現
法的整理は手続きが煩雑で長期化する傾向がありますが、ADRは比較的短期間で進行します。一般的に3~6ヶ月程度で再生計画が策定され、実行に移せるケースが多いです。
例えば、三光マーケティングフーズはADR手続きを活用して、わずか数ヶ月で金融機関との合意に至り、事業再生の道筋をつけることができました。時間は企業再生において最も貴重な資源の一つであり、この迅速性は大きなメリットと言えるでしょう。
3. 柔軟な再生計画の策定が可能
ADRでは、債権者と債務者が対等な立場で交渉できるため、企業の実情に即した柔軟な再建計画を策定できます。リスケジュールだけでなく、一部債務免除、DES(債務の株式化)、DDS(債務の資本的劣後ローン化)など、多様な手法を組み合わせた再生計画が可能です。
具体的には、東日本大震災後に経営危機に陥った仙台の水産加工会社が、ADRを通じて金融機関からの協力を得て、返済スケジュールの大幅な見直しと一部債務免除を実現した事例があります。これにより経営を立て直し、現在では安定した業績を上げています。
4. 経営権の維持が可能
法的整理では、裁判所から選任された管財人が経営の主導権を握るケースが多く、創業者や現経営陣が経営から退くことも少なくありません。一方、ADRでは基本的に現経営陣が引き続き経営に携わりながら再生を進められます。
これは経営ノウハウや人的ネットワークを維持したまま再建できる大きな利点です。老舗旅館チェーンの事例では、創業家が経営を継続しながらADRを活用し、伝統と革新を両立させた再生を実現しました。
5. 公的支援・税制優遇措置の活用
ADRは「産業競争力強化法」に基づく特定認証紛争解決手続として位置づけられており、中小企業であれば信用保証協会による「事業再生計画実施関連保証制度(経営改善サポート保証)」の利用が可能です。
また、一定の要件を満たせば、債務免除益に対する課税の特例措置や、資産の評価損・評価益の計上による税負担軽減なども適用できます。これらの公的支援や税制優遇は、再生の大きな追い風となります。
まとめ:ADRを活用した事業再生の可能性
事業再生ADRは、企業イメージの保全、迅速な再生プロセス、柔軟な再生計画、経営権の維持、公的支援の活用という5つの大きなメリットを持っています。
もちろん、すべての企業にADRが適しているわけではありません。債権者全員の同意が必要という高いハードルもあります。しかし、早期に経営危機に向き合い、適切な専門家のサポートを受けることで、多くの企業が再生の道を切り開いています。
経営危機は終わりではなく、新たな始まりとなる可能性を秘めています。事業再生の選択肢として、ADRという手法をぜひ検討してみてはいかがでしょうか。
【監修者】ブルーリーフパートナーズ
代表取締役 小泉 誉幸
公認会計士試験合格後、新卒で株式会社シグマクシスに入社し、売上高数千億の大手企業に対し業務改善、要件定義や構想策定を中心としシステム導入によるコンサルティングを実施。その後、中堅中小企業の事業再生を主業務としているロングブラックパートナーズ株式会社にて財務DD、事業DD、再生計画の立案、損益改善施策検討に従事。ブルーリーフパートナーズ株式会社設立後は加え税理士法人含む全社の事業推進を実施。
・慶應義塾大学大学院商学研究科修了
